「地域とともに、未来を育てる」ファイティングイーグルス名古屋の実業団時代から変わらぬ想い、地域と共に歩むクラブの姿
実業団時代から地域に根ざした活動を続けてきたファイティングイーグルス名古屋。B.LEAGUE参入後もそのスタンスは変わらず、赤い鷲募金、愛知こどもホスピスプロジェクトへの支援、介助犬との取り組み、カーボン・オフセットなど多様な取り組みを行っています。それらの背景にはどんな想いがあるのか。今回は、鈴木浩昌代表取締役社長、そして現場で活動を先導する工藤雄さん(営業部長・経営企画室)にお話を伺いました。
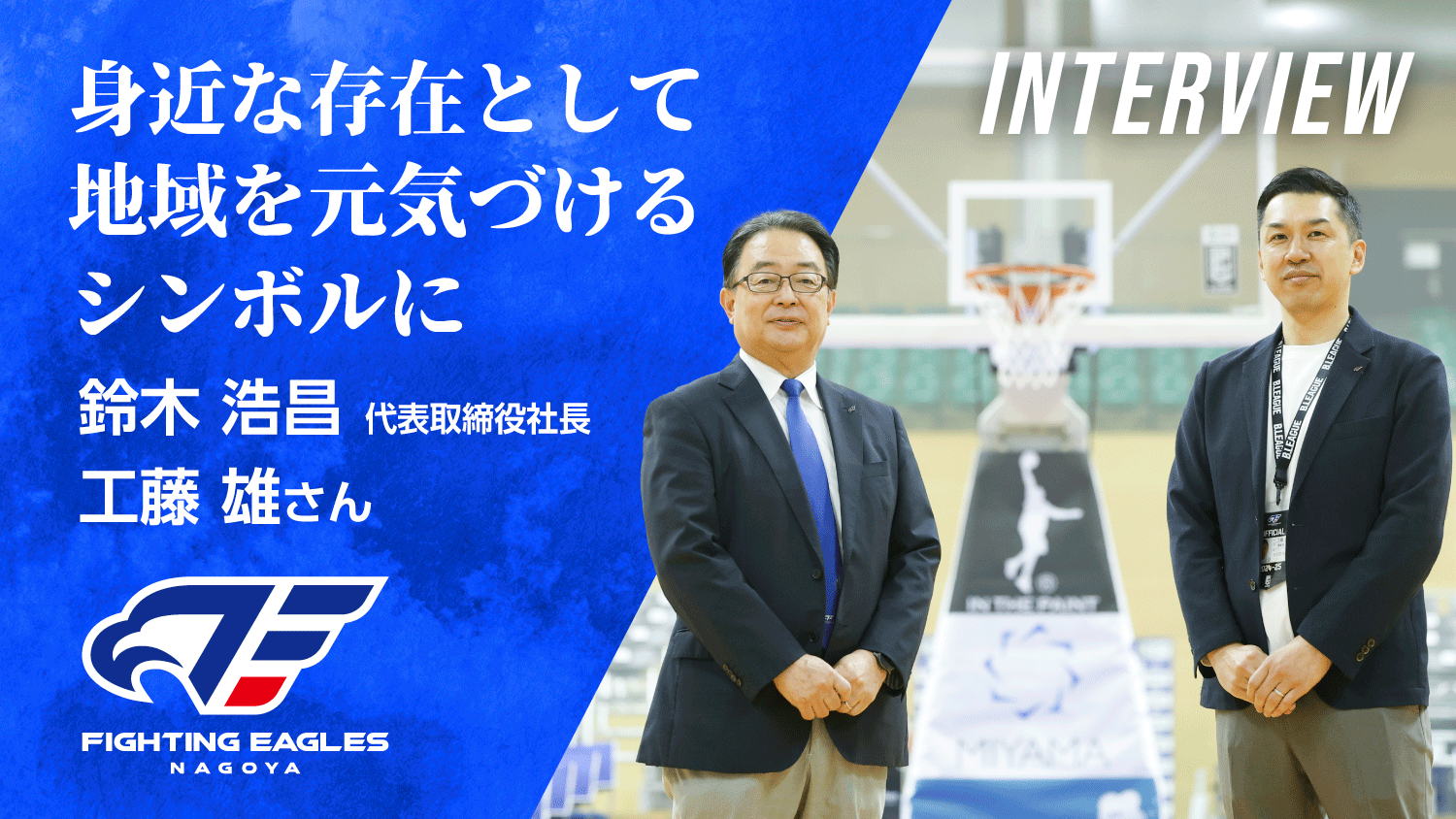
――クラブでは多岐にわたる活動をなさっています。社会的責任活動のコンセプトや方向性を教えて下さい。
鈴木) まず、活動はB.LEAGUEになってから始めたわけではなく、実業団、日本リーグ、NBDL時代から続けてきたことです。我々には「ファイティングイーグルス名古屋は、常に高みを目指し、皆様と共に、Only one のチームであり続けます」というチーム理念があります。簡単に言えば、熱狂体験によって、地域社会の心を豊かにすることです。さらにB.LEAGUE Hopeの理念にも共感しつつ、名古屋市のSDGs、未来都市としての目標も踏まえて「環境(PLANET)」、「人に優しい社会(PEOPLE)」、「防災(PEACE)」という3つの柱を設定しています。地域を盛り上げてつなぐ、チームとしてのバリューを意識して行動しているというのが現在となります。
――鈴木社長は母体となるクラブを90年代からご存知ですね。当時の活動はどんな感じでしたか?
鈴木)当時はSDGsという言葉もなく、地域から要望をいただき、こちらも喜んで行うという形でした。需要や規模も大きくなり、今では毎年100回近くのクリニックを実施しています。当時の子どもたちが大人になり応援に来てくれる状況になっていて、長く関わっている人間としてはうれしい連鎖だなと感じています。

©FE NAGOYA
――身近な存在としてクラブがあった。そういうものが根底にあるわけですね。
鈴木)そうだと思います。ファンの皆さまと選手、スタッフが身近な関係にある。応援に応えて私たちも新しいものを作り出しているというのは強みでもあるし、これからもそうでありたいと思っています。
――特徴的な活動の一つに「愛知こどもホスピスプロジェクト (https://www.achp.jp/)」の支援があります。どんな経緯でスタートしたのでしょうか?
工藤)オフィシャルパートナーである株式会社二友組様からのご紹介がきっかけです。元々、二友組様では、事務所の一角を子どもホスピスさんの事務局として無償提供するなど、多岐にわたる支援を行っていました。オフィシャルパートナーになっていただき、冠ゲームを開催する際に“自社のPRよりも愛知こどもホスピスさんとの取り組みを行ってほしい”という要望をいただいたことから、支援に至りました。
病気と戦うお子さまを勇気づけることもそうですし、不安やストレスを抱えるご家族の力になりたいということで、売り上げを寄付するレモネードスタンドブースを作ったり、コラボユニフォームを作ってチャリティーオークションを実施したりしています。試合にご招待してエスコートキッズを行った際には、とても楽しんでいただきました。まだ調整中ですが、選手が子どもたちを訪問することも実現できればと考えています。

©FE NAGOYA
――エスコートキッズに参加した子どもたちにとっては、エネルギーを得られる機会ですね。
工藤)正に目を輝かせてくれていました。子どもたちもそうですし、保護者の方にとっても“なかなか楽しい時間を作ってあげられていない”という思いがあったようで、子どもたちを見て目を潤ませている姿もありました。またショーン・オマラ選手が積極的に保護者の方と肩を組んで写真撮影をしたりして、参加者の皆さまがすごく感激されていたのも印象的でした。

©FE NAGOYA
――子どもたちに対する取り組みが多くありますね。
鈴木)将来のファン作りという狙いがあることも正直なところです。一方で、我々の親会社である豊田通商、そしてグループ全体で「未来の子どもたちにより良い地球環境を届けるために」活動していることもあります。未来を作っていく子どもたちが、心豊かに成長していくことが、地域全体の活力につながるという考えです。子どもたちが見せてくれるキラキラした笑顔は、私たちにとっても力をもらえるものですし、ファイティングイーグルス名古屋を身近に感じていただき、今後も一緒に成長、前進していけるような環境を作りたいと思っています。
――介助犬協会とも連携なさっていますね。こちらも特徴的だと思います。
鈴木)こちらについても、豊田通商として20年近く活動を続けてきていることの一つです。介助犬の訓練センターは愛知県長久手市にあって、そこから全国に派遣されるという地理的なご縁もあり、人々が集まるホームゲームで啓蒙活動をすることになりました。実際に介助犬がアリーナに来場し、より多くの方に存在や状況を知ってもらうことができ、協会の方にも喜んでいただいています。引き続き、豊田通商と連携しながら認知を広めていきたいと考えています。
――介助犬のピトくんがチームスタッフになっているのも、その一環ということですね。
工藤)介助犬は、障がいを持つ方をサポートする補助犬です。そのPRのためにピトくんにはユニフォームなども用意してチームのスタッフとして入団してもらいました。これにはファンの方に興味を持ってもらい継続的に訴えていきたいという想いがあります。今シーズンは4月26日のホームゲームでアリーナに来場予定で、ハーフタイムに、靴を脱がせたり、落としたスマホを拾ってもらったりという介助のデモンストレーションを企画しています。
また、訓練センターに選手が訪問することもしています。やはり現場を見ることが非常に重要で、選手に介助犬の役割を知ってもらい、彼らが発信することで認知もさらに広まり、メディアに取り上げてもらうことにも繋がりました。
.png)
©FE NAGOYA
――ファイティングイーグルス名古屋ではカーボン・オフセットにも取り組まれていますね。
工藤) SDGsの取り組みの中で、気候変動対策につながる脱炭素化は非常に大きなテーマですし、多くのパートナーの方にも賛同いただいています。ホームゲームで排出されるCO2の量を算定し、その分のクレジットを購入するという取り組みを 行いました。その資金が森林保全などにつながります。継続的に実施し、ファンの皆さまに知っていただき、意識を高めることで、公共交通機関を利用するなどの行動につながればと思っています。
鈴木)ファイティングイーグルス名古屋では「ボトル to ボトル」というペットボトルの水平リサイクルの取り組みも始めました。

©FE NAGOYA
――様々な活動をする中で、選手の意識や熱量というのはいかがですか?
工藤)個々の選手の意識付けにはつながっています。具体的なアクションをしている選手が内尾聡理選手です。自身がひとり親家庭で育った経験から、「S.U future」を立ち上げて同じ境遇の子どもたちの未来に役に立ちたいと活動をしています。クラブとしても継続のためのサポートはしており、例えば、B.LEAGUEのバレンタイン企画モテ男No.1決定戦の写真とクラブのオフィシャルカメラマンの撮影した写真から選べるフォトブックを作って販売し、その収益をS.U futureに寄付しました。今後も協力していきたいと思います。

©FE NAGOYA
――最後に、今後の活動についての思いを教えてください。
鈴木)冒頭から申し上げていることにつながりますが、すべての活動はパートナーがいて、ニーズや問題に向けて組み立てていくものです。活動の幅を広げるためにも、新たなパートナーや連携先も模索し、地域課題の解決を図っていきたいと思います。忘れてはいけないのは、身近な存在であり続けること。我々のバリューを生かして、地域を元気づけていけるシンボルとして歩んでいきたいと思います。

©FE NAGOYA

