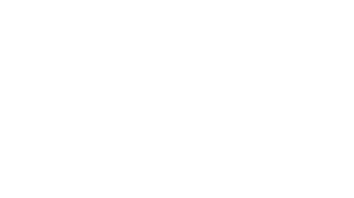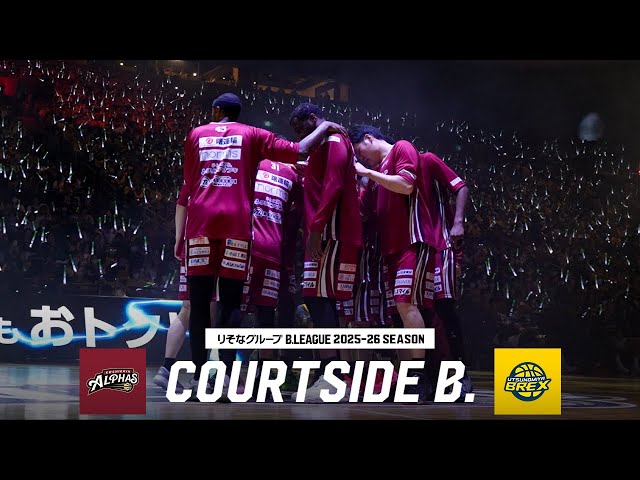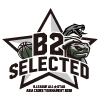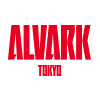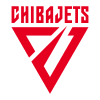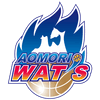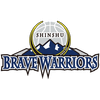クラブの未来を創るGMに求められるもの「第1回B.LEAGUEクラブ組織デザイン勉強会」
“親会社なし”で成長を遂げたファジアーノ岡山が示す組織のリアル
7月22日、B.LEAGUEオフィス及びオンラインを通じて「B.LEAGUEクラブ組織デザイン勉強会~チームを強くする組織とGMの在り方~」が開催された。この勉強会は2026年から本格化する「B.革新」を前に、各クラブのGM(ゼネラルマネージャー)設置とその在り方を学ぶ場として企画されたもの。講師として招かれたのは、Jリーグ・ファジアーノ岡山を運営する木村正明氏(オーナー)と服部健二氏(GM)。2時間を予定していた勉強会は、熱の入った内容により大幅に時間をオーバーすることとなった。
B.LEAGUE常務理事である増田匡彦氏が開催の背景を説明し、勉強会がスタートした。増田氏は「そもそもGMとは何か? その役割を明確に定義する必要がある。現在、選手の稼働に制約が生じてきていることも把握しており、事業部門とチーム現場の連携がこれまで以上に重要になっている。成績はもちろん、地域貢献や事業の売上規模、ファンベースの拡大など多岐にわたる内容を知るGMの存在こそが、B.LEAGUEの成長を支えると考えている」と述べた。
19年間クラブの運営を行ってきたオーナーの木村氏は、ファジアーノ岡山の特異性について説明。「岡山は親企業を持たない珍しいクラブで、スポンサーは6社400万円からスタートし、今年のJ1昇格で売上35億から40億円に到達。1億円以上のスポンサーはほぼおらず、100万円以上のスポンサーが200社近くあります」と具体的な数字を示した。そのうえで親企業を持つJリーグクラブの組織構造について課題を指摘。「利益が出た場合、翌年親会社から得られる資金がその分減る」という構造は成長要因と捉えることもできるが、100億円クラブを作る上では阻害要因にもなり得ると考えを示した。また、事業部門と強化部門のコンフリクト(軋轢)も永遠のテーマだと語り、あるクラブでは孤立を防ぐために情報発表前に全スタッフに共有するといった配慮をしていると事例を挙げた。木村氏は、Jリーグ全クラブの社長在任期間を分析した結果も提示。社長在任期間が長くなると競技成績が低下する傾向に触れ、適切な在任期間は短く、その意識を持つことが大切だと述べた。自身も、事業をさらに伸ばすため、売上15億円の時点でバトンタッチを決断しており、それはこうした分析に基づくものだったと語った。
GM像に「正解はない」と語った服部氏
続いて登壇した服部氏は、複数クラブでGM職を歴任してきた経歴を活かし、GMを4タイプに分類して解説。主に強化部とトップチームを対象に仕事をする①「強化部長(編成部長)タイプ」、主に強化部と育成部を対象に仕事をする②「強化育成部長タイプ」、主に強化部と育成部に加えて普及部も対象に仕事をする③「フットボール本部長タイプ」、①または②に加えて経営・事業系業務も兼務する④「経営参画型タイプ」に分けられるとした。自身は③と④の中間だが、④が理想ではないかとも考えていると話したうえで「これは自身の考えであって、正解というわけではない」と付け加えた。
服部氏はクラブの段階的成長についても独自の見解を示した。「普及期(フェーズ1)」「育成期(フェーズ2)」「強化期(フェーズ3、4)」と4段階に分けられるという自説を展開し、岡山はフェーズ3に当たると認識していると話した。さらなる成長を図るためにも、フットボール部門が創出した価値を事業部門がいかに活用するかが大切とし、そのためには現場と経営のコミュニケーションが不可欠と考えていると述べた。加えて、選手教育の重要性も強調した。シーズン前のミーティングで、クラブのフィロソフィーや各部門の考え方を説明し、選手たちにクラブが目指す方向性を共有。中国ダービーと呼ばれるサンフレッチェ広島戦で勝利した際は、意義を選手に説明し、勝利給を倍にして労ったというエピソードも披露した。こうした取り組みを通じて、選手に稼働への理解と協力を得ているとも明かした。
クラブに合ったGMの形を見出す必要性
聴講したB.LEAGUEフロント陣の反応はどうだったのか。かつてサッカー界で仕事をしていた川崎ブレイブサンダース・川崎渉社長は「理想モデルを目指すという考え方もある一方で、規模によって答えは変わってくる。答えがない話だからこそ、この道で行くと信じて、効果を最大化するために頑張るしかないと改めて感じた」と感想を述べた。またアルバルク東京・伊藤大司GMも「答えのない議論。だが模索しながら理想のGM像を作っていきたい。選手出身である自分はチーム強化には明るいが、経営面をもっと学ぶべきだと感じた時間になった」とコメントした。勉強会の中で、木村氏と服部氏は「正解はない」と何度となく強調している。単にJリーグ流、ファジアーノ岡山流を踏襲するのではなく、クラブに合った形を見出すことこそが、B.LEAGUEのクラブ経営者に求められることのようだ。
冒頭でも触れたとおり、B.LEAGUEは「B.革新」に向けて、GMを配置することを義務化する方針だ。それは単に組織図上の変更ではなく、クラブの在り方そのものを問い直す取り組みでもある。事業と強化のバランスを取りながら、地域に根ざした持続可能な成長を実現する。そのために必要なのは、正解を探すことではなく、クラブに合った方向性を見つけ、それを信じて実行する勇気なのかもしれない。今回の勉強会は、年間5回を予定しているうちの1回目。今後も継続的な学びと議論を通じて、日本のプロスポーツ界全体の発展に寄与する組織デザインが模索されていくことになるだろう。