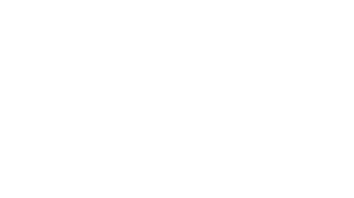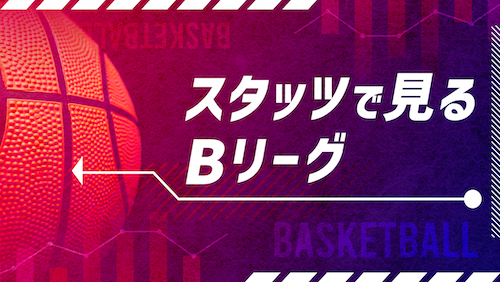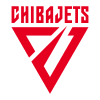加藤誉樹レフェリーインタビュー「B.LEAGUEでの取り組みが自分の成長につながっている」 B.LEAGUE 10周年記念

2017年9月に初めてJBA公認プロフェッショナルレフェリーとして採用された加藤誉樹レフェリーはB.LEAGUEとともに歩みを進め、9年連続で最優秀審判賞に輝くなど、日本を代表するレフェリーとして活動を続けている。加藤レフェリーは10シーズン目を迎えたリーグの成長をどのように感じているのか。2026年秋に始まる『B.革新』への期待も含め語ってもらった。
B.LEAGUEの成長は「想像をはるかに超えてきた」
――B.LEAGUEが開幕してから10シーズン目を迎えました。分裂していた2つのリーグが統合し、日本にプロバスケットボールリーグが誕生すると聞いた時はどのような感想を抱きましたか?
加藤:当時はどのようなリーグになるのか未知数で、今のような姿になるのは想像もできませんでした。興味とワクワクの気持ちが強かったです。私はNBLを担当していましたけど、代々木第二(国立代々木競技場 第二体育館)が満員になることは少なかったと記憶しています。今では倍か、それ以上の入場者数ですから、想像をはるかに超えてきたなと思っています。
――2016年9月22日に行われたアルバルク東京vs琉球ゴールデンキングスの一戦で幕が開けました。
加藤:私は画面越しで試合を見ていましたが、やはり印象深いのは全面LEDコート。今でこそ海外で見る機会はありますけど、世界初の試みとして注目を集めました。バスケットボールのエンターテインメント性があのような形で表現されるのは非常に新鮮でしたし、新たに始まるB.LEAGUEにワクワクしました。あの場にいなかった身としては、全面LEDコートでレフェリーを担当するのはどんな感じなのか興味がありましたね。今では新アリーナが全国各地に誕生し、それぞれに特色があります。試合前は緊張していたり、緊迫感のある精神状態ではあったりするものの、各クラブが様々なオープニング演出を見せていて、私自身も楽しみにしています。

――大きなアリーナで、多くの観客の前で笛を吹くのはいかがですか?
加藤:どのアリーナでもコートの大きさは縦28メートル、横15メートルです。コートに入って試合が始まれば、B.LEAGUEでも、オリンピックやワールドカップといった国際大会でも、感覚的にはそこまで変わりません。一方、入場者数が1万人規模の試合になると、笛の音が聞こえないという実務的な苦労もあって。ワールドカップやオリンピック、NBAの試合ではレフェリーが笛を吹くと、自動的にゲームクロックが止まるシステムを採用しています。以前はファイナルのような大舞台が大半でしたけど、最近はレギュラーシーズンでも聞こえない試合が増えてきました。盛り上がりと表裏一体な部分だと思うので、そういったテクノロジーも必要な規模になったと感じています。
――意外な苦労もあるのですね。
加藤:ただ、落とし穴になりそうな部分を埋めるべく、レフェリーとTO(テーブルオフィシャルズ)さんが一体になって、そのシステムがなくてもできる限り最大の努力をしています。笛が聞こえない時、我々が頼りにしているのがシグナルです。例えば、手のひらを開くのはゲームクロックを止めるシグナル、片手のこぶしを握るのはファウルでゲームクロックを止めるシグナル。そこはTOさんがしっかりとゲームクロックを止められるように、試合前のミーティングでコミュニケーションを取り合っています。あとはショット成功後の大歓声でタイムアウト請求のブザーがレフェリーに届かず、レフェリーが試合を止められずに進んでしまうことを防ぐため、TOさんにはゲームクロックをまず止めて、歓声が収まるまでブザーを鳴らし続けることもお願いしています。笛が聞こえなくて、ゲームクロックを止められなかったことをTOさん自身が認識したら「それを恥と思わずにレフェリーに伝えてください。IRS(インスタントリプレーシステム)を使って、正しい時間に直して再開します」といったことまで話しています。

判定の制度とともに求められる“コミュニケーションのクオリティー”
――島田と語りまショーに出演した際、競技のレベルが上がっていて、バスケットボール自体も変化しているという話がありました。具体的にはどのような変化を感じますか?
加藤:10年前も元NBA選手がいましたけど、今はコーチを含め外国籍のレベルがとても高いと感じます。例えば先日のFIBA ユーロバスケット2025にもB.LEAGUEの選手やコーチが出場していて、大会に派遣された私は会場で彼らに挨拶する機会がありました。国際大会で「こういった場所で会えるのは本当にうれしいよ」と話してから試合が始まることも増えています。私自身が感慨深さを感じるとともに、B.LEAGUEはこの舞台に立つ選手やコーチが活躍するレベルまで達しているんだなと。それに付随するように日本人プレーヤーも成長しています。また、U15やU18といった育成年代の取り組みもリーグの後押しにつながっていると思います。
――競技のレベルが上がるとともに、ジャッジの部分でも質の高いものを求められていると思います。
加藤:判定の精度はもちろん求められます。また、試合の真剣度が増せば増すほど、私たちの判定においてどうしても難しい場面があります。例えば、プレーヤーとコミュニケーションを取って説明しなければ、状況をスムーズに進められないシチュエーションもあって、特に外国籍プレーヤーとのやり取りの頻度が格段に増えたと感じます。前身のリーグではレフェリーが話を聞いただけで満足してくれたというか、ある種の収まりがついていたのかなと。今は、聞くだけではもちろん不十分です。私自身はどのような内容の話を返すのかにこだわっていて、伝えたいことをナチュラルに受け取ってもらえるような表現の工夫でも高いクオリティーを求められていると感じます。単に英語を聞ければいい、英語でコミュニケーションを取れればいいではなく、それらを超えなければいけない局面が増えています。
――外国籍の選手やコーチとのコミュニケーションで印象に残っていることがあれば教えてください。
加藤:私は昨シーズンの千葉ジェッツ対宇都宮ブレックスの第1節を担当しました。アリーナを出る動線が2連敗した宇都宮の選手やスタッフと同じになり、当時のヘッドコーチだったケビン(ブラスウェル)さんとばったり出口でお会いしました。「2日間ありがとうございました。自分たちが完璧ではないことを認識しています。試合を振り返って、改善すべきところはどこだったのかを省みたいです」と伝えたところ、ケビンさんから「完璧な人間なんていない。自分が今日の試合でHCとしていくつのミスをしたと思う?」と。
HCはレフェリーの判定に対して、いろいろと思うことが多いと勝手に思っていた一方、ケビンさんが私たちを非難する代わりに、自分の失敗も引き合いに出し、「バスケットボールの仲間として、ミスや失敗も含め、みんなで一緒に試合を作っているんだ」と話してくださいました。この言葉を聞いたからといって、私自身の取り組みが変わったことは一切ありませんが、彼ともっとバスケットボールの話をしたい、彼と一緒にコート上で仕事をしたいと心から思いました。その後、2月に彼の訃報を知ることになってしまったのですが……。この夏、私はニュージーランド代表の試合を担当する機会があり、「彼は素晴らしい人間だったね」と、コーチ陣とケビンさんのことを話す機会がありましたね。(※ケビンさんはかつて選手、コーチとしてニュージーランドのクラブに在籍)
――様々な国際大会でもレフェリーを務めてきましたが、印象に残っている試合はありますか?
加藤:パリ2024オリンピックでのアメリカ代表対南スーダン代表戦ですね。アメリカ代表選手にアンスポーツマンライクファウルを宣告した際、判定とルールを巡ってNBAの偉大な選手4人(レブロン・ジェームズ、ケビン・デュラント、ステフィン・カリー、アンソニー・デイビス)とコミュニケーションを取ったら、そのやり取りが写真に収められていまして。私にとってはレフェリー人生のハイライトの1つになるような場面でした。ただ、実は彼ら4人が私のそばにいて、話している感覚が一切ありませんでした。B.LEAGUEの試合と同じように、選手とコミュニケーションを取っていただけで、たまたまあのような写真が生まれたんです。試合が終わるまで全く認識していなかったので、ロッカールームに戻ったら、スマートフォンにものすごい数のメッセージが届いているのを確認しました。そこで初めて「彼ら4人が私の近くにいて、コミュニケーションを取っていたんだ」と。選手が誰であろうと、特別扱いしないことを大事にしていますが、世界中に知られているNBA選手たちという意味では、人生の1つのハイライトになるような瞬間だったと思っています。

――B.LEAGUEの1試合でも、国際大会の1試合でもすべて同じ感覚ということですね。
加藤:おっしゃるとおりです。ただ、なかなかそのように思ってもらえないことも多くて。「緊張しましたか?」とよく聞かれますが、実はどの試合でも緊張するんですよ。自分のパフォーマンスが落ちるほどの緊張はない一方、すごくリラックスして、緊張していないという試合もなくて。いい緊張感というか、集中力を持ち、自分の最大限を発揮できるように意識しています。
――島田チェアマンとの対談では「レフェリーのメンタルコントロール」についても言及されていました。シーズン中はどのようにメンタルを整えて、試合に臨んでいますか?
加藤:その点は自分として課題に感じていて、解決策を見出すのがなかなか難しくて。1日24時間、1週間7日、1年間365日は誰もが同じ時間です。試合への準備、試合の振り返りには時間を要する一方、そこにかけられる時間も限られていて、ジレンマを感じる部分は多くあります。最近になって感じるのは、オンとオフの切り替えというか、メリハリがすごく大事だなと。シーズン中はリラックスする時間をなかなか作れず、常にバスケットボールのことを考えていて、夢にも出てくるほどです。いいパフォーマンスを発揮するための大事な要素の1つとして、いかに休養を大切にできるのか。まだチャレンジしているところですけど、限られた時間でどのように取り込めるのかは大事にしなければいけないと思っています。
『B.革新』とその先へ…「レフェリーのレベルも常に上げていかなければ」
――B.LEAGUE10周年目を終えると、『B.革新』という次のフェーズへ突入します。レフェリーの立場として注目していることはありますか?
加藤:バスケットボールは考案されて120年ほどという比較的若いスポーツです。選手の能力や技術は日々進歩していて、それに併せてルールも変わっていきます。競技のレベルに伴い、レフェリーのレベルも常に上げていかなければいけません。
私たちB.LEAGUE担当のレフェリーもコツコツと向上していくことがまず1つ。より注目が集まれば、リーグ全体のレベルも上がっていくと思っています。今のプロフェッショナルレフェリーは合計9名で、来シーズン以降も増えていくと思っています。1つの大きなグループになっていくという意味で、仲間意識を持って取り組んでいきたいです。ただ、プロのレフェリーがいくら増えても、別の仕事を掛け持ちしながらレフェリーを担当してくださる皆さんがいることも忘れてはいけません。彼らがいなければ、自分たちの仕事は成り立ちませんから。
私もB.LEAGUE1年目は一般企業で働きながらでしたので、かなり大変だったことを記憶しています。リーグが成長を続けるなか、ほかの仕事もこなしながらレフェリーとしてコートに立つのは非常に難しいことです。でも、誰かが担当してくれないと、素晴らしいバスケットボールを届けられません。彼らがやってくださっているのは稀有なことで、貴重なこと。バスケットボールに関わる全員が彼らのことを大切にしなければいけないと思っています。プロの世界に入ってみて、彼らの人間の幅というか、素晴らしさをより感じます。限られた時間でも最大限努力し、このコートに求められるレベルをクリアしようと日々取り組まれていて、頭が上がらないですね。

――プロレフェリーを目指す方が増えていると聞きました。ご自身の立場からアドバイスがあれば聞かせてください。
加藤:カッコいいことを言えば、楽しむことが大事。私もコートに立たせてもらっていますが、これはシビアになってくると忘れがちで、しんどいことばかりに目がいってしまう時期もあります。自分が前へ進む原動力になるのは、バスケットボールが好きとか、レフェリーが楽しいと思えるかどうかです。実務的な話ではレフェリーのスキルと同時に、語学や体作りも求められます。今後はより高いレベルが必要だと感じているので、プロを目指す方には早い段階からそういった部分にも着手してほしいです。
――最後に、加藤レフェリーの今後の目標を聞かせてください。
加藤:目標を聞かれる機会は少なくないんですが、実は答えるのが難しくて。遠い未来を見て、何かに取り組むということを言わないようにしています。あくまで次に担当する試合に対し、担当するレフェリーと協力して、無事に終わらせられるのか。私はそこにフォーカスしています。2027年のFIBAバスケットボールワールドカップ、2028年のロサンゼルスオリンピックを担当できればいいなと思いつつ、目の前の試合をないがしろにすることはしたくありません。話は変わりますが、今回のFIBA ユーロバスケット2025に行って思ったのは、日々のB.LEAGUEでの取り組みが自分の成長につながっているんだなと。自分が何かを変えなくてもコーチと自然にコミュニケーションを取れたり、ゲームをスムーズに進めることに貢献できたり。海外の大会だから、ヨーロッパ最高峰だからといって、特別なことをする必要がありませんでした。B.LEAGUEのレベルが上がっている分、そこでの経験や取り組みが海外でも活かされていると感じました。そういった意味でも日々の1試合、1試合を大切にしていくことが自分自身の成長につながり、国際大会を任せていただけることにもつながると、確信を持って言えます。リーグの成長は我々レフェリーの成長につながりますし、我々の成長がリーグをより良いものにしていくことにつながると思っています。
インタビュー・文=酒井伸
構成=バスケットボールキング